こんにちは、石倉です。
今回は僕が作曲をするときに、一番エネルギーを使う部分と言っても過言ではない、曲の始まりの部分の作曲について話します。
なぜ、曲の始まりの部分にそんなにエネルギーを使うのか。
それは、曲の始まりの一瞬で曲の印象というのは8割位決まってしまうものだからです。
曲の始まりを人に例えると第一印象
曲の始まりというのは、人に例えると第一印象です。
第一印象というのは大きく、「〇〇なひとだなあ」の〇〇の部分って、ほとんど第一印象で決まってしまいますよね。
それは曲も同じで、曲の印象は冒頭で決まってしまうと言っても過言ではありません。
だから、最初の音を選ぶのはとても緊張します。
考えられる最善の音を探すんです。
頭の中にある何万通りかわかりませんが、試せるだけ全部音にしてみて、自分の感覚ととにかく相談。
「さっきの音のほうが曲のイメージになっていたなあ」とか、「半音ずらしてみよう」など試せるものはすべて試します。
最後まで聴いてくれるかどうかが決まる
新曲ができたよ!というと大体の人は最初の部分は聴いてくれます。
しかし、そこで飽きられてしまったりつまらないと思われてしまったら…
肝心のサビの部分まで聴いてくれません。
なので、最初の部分をしっかりと作り込むのは、最後まで曲を聴いてもらうためでもあるんです。
これはクラシックに限らずポップスの世界でもよく言われているそう。
「サビまで聴いてもらうかが勝負。イントロをなるべく短くしてすぐにボーカルを入れるんだ。」
というのを聞いたことがありますが、まさにそうですよね。
最近の曲は昔の曲に比べて、やたらとイントロが短いんです。
イントロを短くしすぐにボーカルを入れることで、飽きさせることなくサビまでなんとか聴いてもらおう、ということ。
これはクラシック曲を書くときにも、大いに参考になりますね。
僕が気をつけているのは、コード進行で飽きさせないということ。
予想通りに行き続ける音楽は、すぐに飽きてしまうものです。
だから、みんなが予想しないだろう、みたいな方向に少しだけ舵を向ける瞬間をどの曲にも作っています。
おわりに
作曲をするときに、どの部分にどのくらいのエネルギーを使うのか。
改めて考えてみると、僕の場合は曲の冒頭にほとんどエネルギーを使っていました。
こうしてブログに書いてみると、自分でも言語化してなかった部分が沢山発見されて、書いている方もとても楽しいですね。
改めて作曲って楽しいな!と思いました。

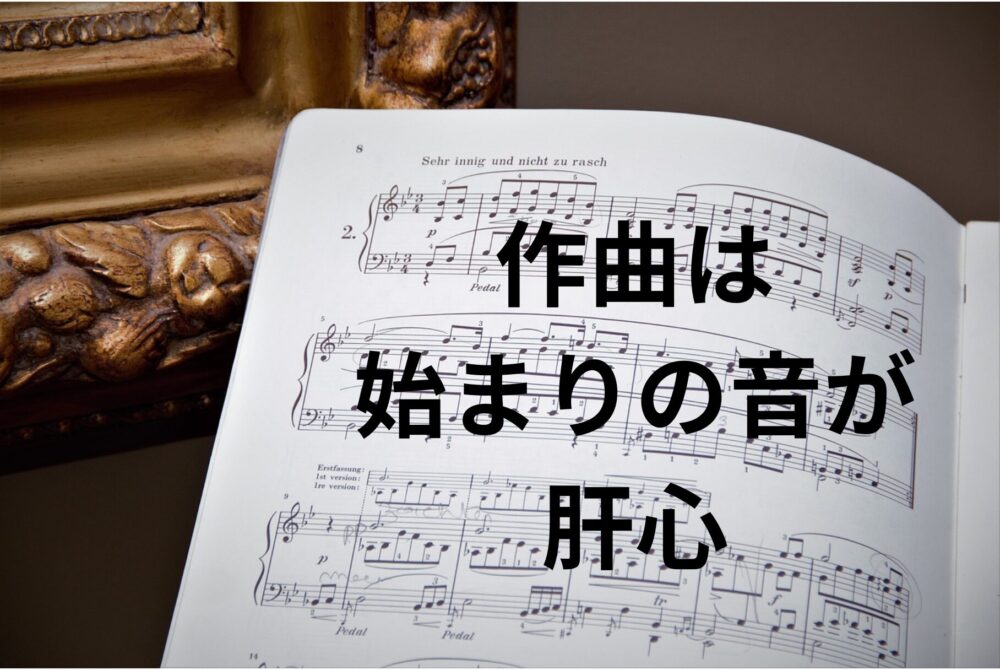
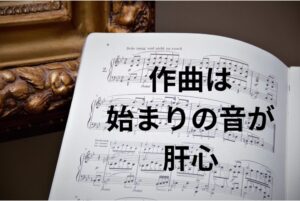
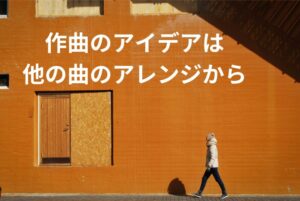

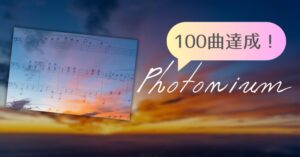
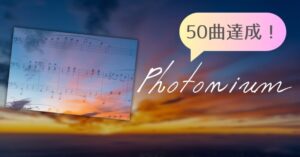
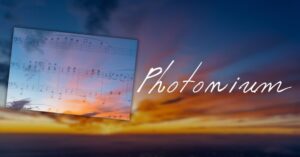
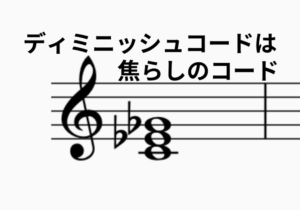
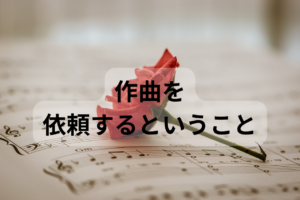
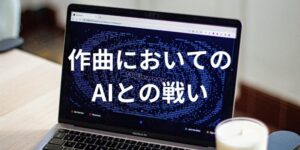

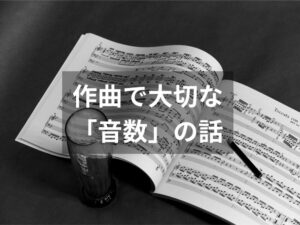
コメント