こんにちは、石倉です。
普段オーケストラは聴きますか?
僕は普段色々な楽器の作曲・編曲をしていますが、今年の2月には原作20周年記念『「らき☆すた」オーケストラコンサート〜20周年だよ、全員再集合!~』 で編曲を担当したりと、たまにオーケストラ編成の作曲・編曲活動をしたりもします。
僕は主に吹いている楽器がユーフォニアムということもあり、オーケストラで演奏する機会はあまりありません。
そのため、吹奏楽に比べると作曲・編曲で苦労することも多いんです。
今回はそんなオーケストラの作曲・編曲をする上での話をしたいと思います。
オーケストラの編成は人間の耳に最適な編成だった
昔から有名なクラシック作曲家はほとんどと言っても過言ではないくらい、オーケストラ編成を使った交響曲を書いています。
一体なぜなのか。
僕もオーケストラ編成で作曲・編曲をするまでよくわからなかったのですが、自分で書いてみるとその謎が解けました。
それは、オーケストラ編成は限りなく人間の聞き取りやすい音域を全てカバーしているということ。
これどういうこと?となる方いると思うのですが、ピアノを想像してみるとわかりやすいと思います。
ピアノってある時代までは鍵盤の数が増え続けていたのですが、黒鍵も含めて88鍵という数は時代とともに増え続けていかなかったわけです。
なぜ増えないのかというと、ズバリあんまり意味がないから。
あんまり高すぎたり低すぎたりしても、人間の耳にとっては音という認識ができなくなってしまうんですね。
この点においてオーケストラの音域は人間の耳にぴったりの音域をカバーしているんです。
そしたら吹奏楽はどうなの?と質問されそうですが、吹奏楽の場合オーケストラに比べて中音域に厚みがある分、高音域はやや薄い特徴があります。
もちろん一概には言えませんが、なぜオーケストラ編成が人気なのかは、人間の耳との相性とも考えられそうです。
弦楽器を書くのはユーフォ奏者にとってはなかなかハードルが高い
僕は今までユーフォニアムを中心に楽器を演奏してきました。ユーフォニアムは金管楽器に分類され、唇の振動を楽器に伝えることで音を出しています。
しかし、弦楽器の音の出る仕組みは金管楽器とはまるで異なりますよね。
唇の振動ではなく、弦の振動だし、息ではなく腕を動かすことで音を出します。
この自分があまり演奏したことがない楽器を書くというのはなかなか大変なんです。
というのも自分が普段吹いている楽器であれば、この辺りの音並んだらきついよなあとかいろいろ感覚でわかるわけです。
それがわからない分、とても頭を使って書きます。
どの音域がその楽器にとって演奏しやすいのか、めちゃくちゃ研究するんですよ。
それこそ、その楽器のソロ曲を聴きまくったり、実際に奏者に質問しまくりです。
それでも頭の中の再現度はオーケストラが抜群
難しい部分も多々ありますが、それでもオーケストラ編成で作曲・編曲した時の頭の中にある音楽を再現できる度はとっても高い!
それこそユーフォニアムの作曲だってとても好きですが、ユーフォニアムの音域に制限を感じてしまうことも実はあったりします…。
その点、オーケストラなら高音から低音まで楽器が網羅されている分、とっても作曲・編曲しやすいんです。
オーケストラの魅力にハマってしまう昔の作曲家たちの気持ちがよくわかりますね。
おわりに
作曲・編曲活動は、編成によってとても自由度が変わってきます。
もちろん、制限がたくさんある編成もそれはそれで制限の中でいかに楽しく書くかと燃えたりもするのですが(笑)。
それでもやっぱり、オーケストラの自由度は格別。
ぜひ今後とも挑戦したい編成です。

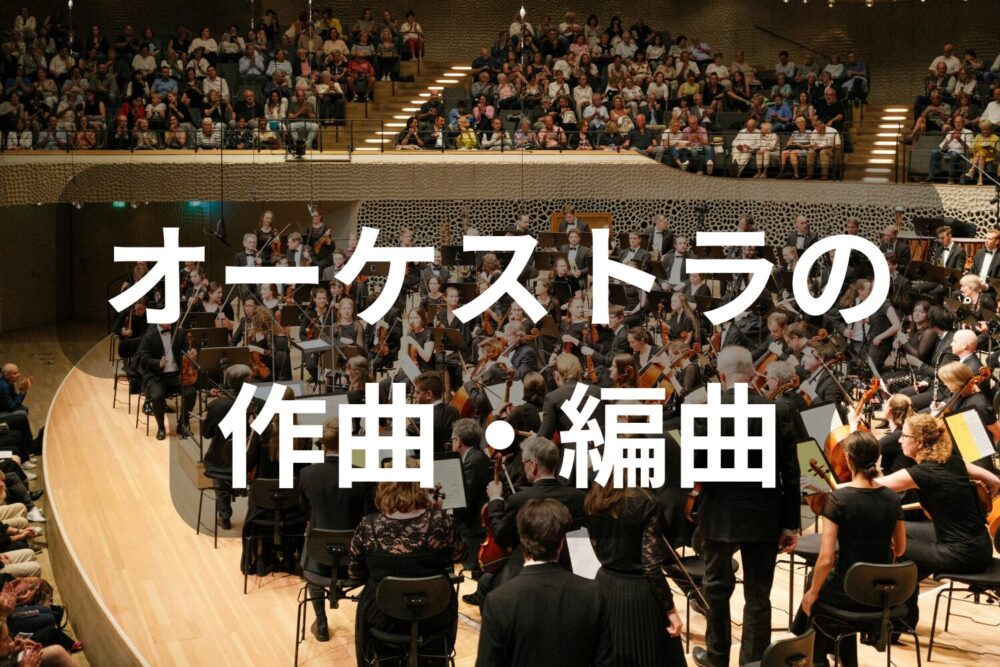


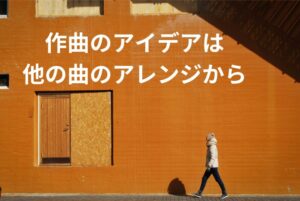
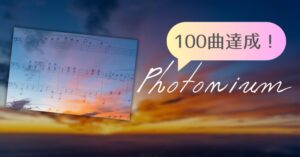
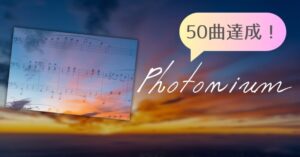
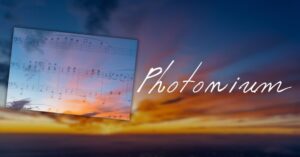
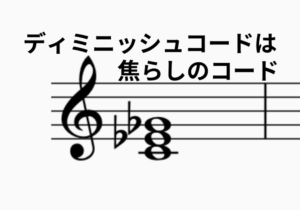
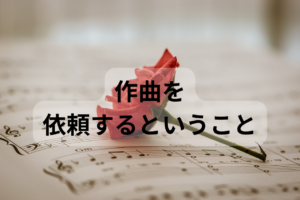
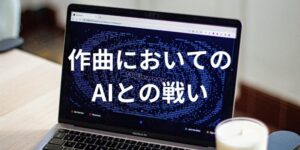

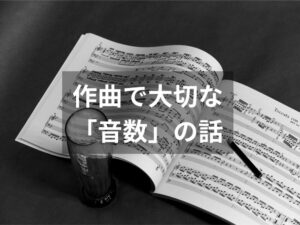
コメント